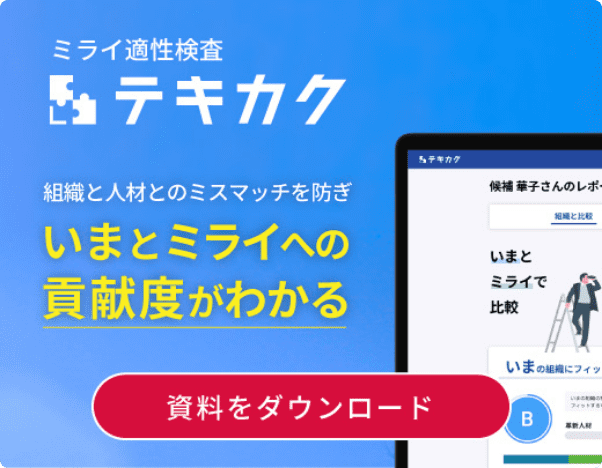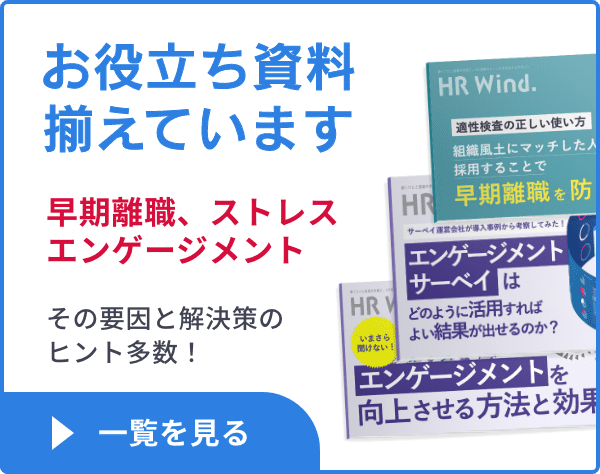モチベーションの向上や維持は労働生産性の向上や人材育成につながるため、マネジメントにおいて押さえておきたい手法です。
しかしその一方で、
「モチベーションを上げるにはどうしたらいいんだろう」
「維持させるのがなかなか難しい」
このような悩みを抱える方も多いかもしれません。
そこでこの記事ではモチベーションの概要や維持させる方法、部下のモチベーションを向上させるポイントについて解説します。部下を持つ上司や、人材管理に携わる人事担当者の方はぜひお役立てください。
1. モチベーションとは?
まずはモチベーションの概要について以下の項目に沿って解説します。
- モチベーションには2種類ある
- モチベーションが低下してしまう理由
それぞれ内容を確認しておきましょう。
モチベーションには2種類ある
一般的にモチベーションとは、「やる気」「意欲」「動機」などの意味で用いられる表現です。ビジネス上においては仕事への意欲を引き出す動機付けとして用いられます。モチベーションは目標達成を目指す原動力や個々の主体性を発揮する源となります。そのため管理職や人事担当者には社員のモチベーションを向上させ事業運営に生かす取り組みが求められるのです。
またモチベーションを動機付けと捉えると「外発的動機付け」と「内発的動機付け」の2種類に分けられます。
外発的動機付け
外発的動機付けとは、外的報酬を得るために行動を取っている状態です。外的報酬とは例えば賞与や目標達成、資格取得などを指し、「試験に合格するために勉強する」などが具体例として挙げられます。特徴としては短期間で行動が変わりやすい即時性があります。外的報酬に対し慣れてきた場合や結果が得られにくい場合には持続性が弱まるため、効果は一時的なものと捉えられるでしょう。
内発的動機付け
内発的動機付けとは、内面における興味・関心が動機付けとなっている状態です。具体的には報酬として得られるものはない趣味の活動などが挙げられます。結果として得られるもののために行われる活動ではなく、活動そのものに興味や関心が強い状態によって行動が促進されます。
そのため外発的動機付けよりも持続性が高く、企業としては内発的動機付けを刺激するような施策を講じることが社員へのモチベーションの向上や維持に有効です。
モチベーションが低下してしまう理由
社員のモチベーションが低下する理由として大きく2つ紹介します。
- 仕事に魅力を感じていない
- 正しく評価されていないと感じている
まず「仕事に魅力を感じていない」状態では、社員が仕事を「やらされている」と感じやすく仕事へのやりがいや楽しみを感じられない状況です。例えば、自身のスキルを発揮できない環境や、希望にそぐわない人員配置であるとモチベーションが低下します。
この場合、企業の対策としては、社員個々に適切な目標を設定する対策が必要です。目標を達成する意味合いやプロセスを確立させることに加え、社員自身の要望を踏まえた目標を設定することで目標達成に向けやりがいを持って仕事に取り組みやすくなるでしょう。しかしいくら目標に向かって励んでいても「正しく評価されていないと感じている」状態では社員のモチベーションは低下します。なぜなら成果を上げても変わらない評価を下される環境や、努力や取り組みを認められない環境ではやる気がなくなってしまうためです。
そのため企業は社員全員が評価に納得できる評価基準の設定や見直しが必要です。納得感が得られる評価は学びが多く、次なる目標達成に向けてモチベーションを維持しやすくなるでしょう。
2. モチベーションを維持する5つの方法
モチベーションを維持させる4つの方法を紹介します。
- 企業方針を全社員に浸透させる
- 職場環境を整える
- キャリアデザインを明確に設計する
- 社員と定期的に面談を行う
- 適切な目標設定をサポートする
1つずつ詳しく確認しましょう。
企業方針を全社員に浸透させる
1つ目は全社員に企業方針を浸透させる方法です。企業方針を浸透させ社員から共感を得られると、経営層と従業員が同じ方向性を向いて事業戦略を捉えられます。その結果社員は新たな事業や与えられた取り組みに対し意欲的に行動でき、モチベーション維持できるのです。
具体的な方法としては、経営層から企業方針を直接共有する機会の提供や、企業方針を体現できているかを評価する人事制度の設定が挙げられます。また採用時に経営理念や企業文化への共感を基準として設けると、企業方針を浸透させやすい環境が整います。
職場環境を整える
2つ目は職場環境の整備です。長時間労働の常態化や嫌がらせが横行するような職場は社員の心身に疲労を蓄積させ、仕事に対するモチベーションは上がりません。
反対に、例えば仕事と私生活を両立できる勤務時間は社員にとって十分な休息時間が得られることにつながります。また適切なコミュニケーションが活発な職場は社員の自己肯定感を高めることにつながりやすいでしょう。社員にとって適切な職場環境の整備は仕事への活力を保つことができ、やりがいを感じられやすいためモチベーション維持につながるのです。
キャリアデザインを明確に設計する
3つ目は明確なキャリアデザインの設計です。社員自身が望む将来像を実現するために必要なプロセスを明確化することによって、主体的な働きや行動を促すことに期待できます。主体的な働きを通して実現したい姿に近づける過程が可視化できると、内面からやる気が生み出されモチベーションを保ちやすくなります。
具体的な方法としてはまず社員自身が希望するキャリアを深く理解する機会を設け、企業はそれに必要なプロセスを提案するなどの支援を行うと良いでしょう。
社員と定期的に面談を行う
4つ目は社員との定期的な面談の実施です。部下にとって上司との面談は、課題解決への糸口を得られる場や取り組みの軌道修正ができる機会として活用できます。このような効果的な面談を定期的に実施できると仕事へのやる気を高めることができ、モチベーション維持につながるのです。
ただし単に定期的に面談を行うだけでは社員にとって意味を感じられず、逆効果となる可能性もあります。そのため面談を実施する際には予め面談におけるゴールを明確にすることや、部下に面談の事前準備をさせると部下にとって意味を感じられやすく、効率の良い面談として有効です。
適切な目標設定をサポートする
モチベーションを維持するには具体的な目標設定をすることが大事です。明確で達成可能なレベルの目標設定をすることで、すぐに実践しやすく、ゴールに到達した自分をリアルに想像できるようになり、やる気が湧いてきやすいです。
あまりにも非現実的で曖昧な目標設定だと、ゴールに確実に近づいていることを実感しにくく、意欲が長続きしません。
また、仕事の目的「なぜ」の視点を明確化することで、社員は自分のしている仕事が社会に貢献しているものだと認識できます。業務内容をただ淡々と伝えるのではなく、その仕事がどんな意味があるのか上司が部下に丁寧に伝えることで、やりがいを強く感じてもらいやすくなるでしょう。
仕事の意義をしっかりと理解してもらうことは、長期的なモチベーションの維持につながります。
目標設定で重要な「SMART」
目標設定で役立つフレームワーク「SMART」をご存知でしょうか?
目標を掲げる上で大事な5つの指標ですので、是非SMARTについての理解を深め、活用してみてください。
SMARTとは、目標設定を成功させるための5つの要素の英単語の頭文字をとった言葉です。
この5つの要素をそれぞれ解説します。
- Specific(具体的に)
Sは「Specific・具体性」を表します。抽象的な表現ではなく、誰が見てもわかりやすい、明確に想像できるような言葉を使って目標設定をしましょう。具体的な目標を作ることで、そこに達成するまでの日々の行動も具体的になっていきます。
- Measurable(測定可能な)
Mは「Measurable・測定可能性」を表します。目指しているゴールを数値化して測定できるように設定することで、その数値に達成するためには具体的にどんな計画を組めばいいのか算出することが重要です。
- Achievable(達成可能な)
Aは「Achievable・達成可能性」を表します。達成不可能な目標はすぐ諦めてしまう傾向にあります。「現状よりも努力が必要だけれど、頑張れば達成できる」くらいのレベルが最もやる気を継続しやすいです。
- Related(経営目標に関連した)
Rは「Related・経営目標の関連性」を表します。個人の目標が企業の目標とリンクしているか確認しましょう。自分だけの利益だけではなく、個人の掲げたゴールが企業にとっても有益であると意識することで、モチベーションが高まります。
- Time-bound(時間制約がある)
Tは「Time-bounded・時間制約」を表します。目標設定に期限を設けることです。時間制約があることで、先延ばしや後回しなどを防ぐことができます。
3. モチベーションの維持が難しい時の対処方
上記で述べた手法を使っても、社員のモチベーション維持を保つのが難しい場合があるかもしれません。長期的に仕事へのモチベーションを維持させるには、下記2つの手法を使うのも良いでしょう。
休息を取る
モチベーションを無理に保とうとするのではなく、一旦休息を設けるのが長期的に見て効果的です。やる気が湧かないのには、それなりの理由があります。疲労やストレス、過労がある場合は、頑張りたくても頑張れません。
頑張ろうと自分を追い込むよりも、一旦休息をとることで、心身ともに回復され、仕事に対するモチベーションも取り戻せる可能性が高くなります。
しかし、自分が認識している以上に心身が疲労している場合があります。不眠や抗うつ状態などの症状が現れた場合は、仕事を続けるのは危険です。
ただ休むだけではなく、専門医を受診するなど適切な対処が必要な場合があるので、自身の体調をよく確認しましょう。
また、このような心身の不調が深刻化する前に、普段から定期的にリフレッシュの時間を設けるのは、長い目で見て必要な行為です。
本業と離れた活動に携わってみる
普段関わっている業務以外の全く別の分野に関わってみることで、良い影響を受けられます。いつもと違う世界を見ると新鮮な気持ちになり、本業へのアイディアが浮かぶこともあるでしょう。思いがけない場面で仕事の人脈を広げられたり、自身の成長につながるような出来事と出会えたりする可能性もあります。
異なる分野でも、尊敬できる人がいれば、その人のそばに行って観察する機会があると良いインスピレーションを得られるかもしれません。
ボランティアや副業などの本業と異なる活動はリフレッシュにもなります。
本業へのやる気を高めるには、本業以外の生活にも彩りを持たせることが、長期的にみて精神衛生上良いと言えるでしょう。あまり追い詰めすぎずに、余裕を持つことが大事です。
4. 上司必見!部下のモチベーションを上げるマネジメント

部下のモチベーション向上において押さえておきたいコツがこちらです。
- 評価にはプロセスも重視する
- 「それぞれの部下を認めている」ことを表現する
それぞれ内容を確認しておきましょう。
評価にはプロセスも重視する
評価においては部下の成果だけでなくプロセスも重視しましょう。社員にとっては目に見える成果や結果だけでなく自分自身の頑張りが評価されることによって、「自分の努力を認めてもらえている」と感じられます。上司からの支援を感じられるとモチベーションは高まり社員の自信となるため、次なる目標に向け新たな行動の促進につながります。
具体的には、どんな意図をもってその行動に取り組んだかを明確に聞き取れると良いでしょう。意図や目指す方向性に理解を示すことで、部下にとっては自身の頑張りが評価されていると実感しやすくなります。
「それぞれの部下を認めている」ことを表現する
上司からの声がけや気配りは、部下にとって「自分への関心」の実感となりモチベーション向上につながります。部下個々へのコミュニケーションの量を増やせると、部下は「自分に興味や関心を持ってくれている」と自然と感じられ関係性の強化につながります。その結果上司に対する信頼性や貢献したいという意欲が高まり、業務への意欲が向上されるのです。
具体的には、職場で見かけた際には挨拶や短い声かけをすることや、連絡や報告を受けた際には直接お礼を伝えることなどが挙げられます。普段からコミュニケーションの量を増やすことを心がけると良いでしょう。
組織の強みと課題を可視化する 組織改善ツール「ラフールサーベイ」
「あの社員、最近元気がない気がする…」「コミュニケーションをもっと取った方がいいのかな?」とお悩みの管理職や経営者の方も多いのではないでしょうか。
組織改善ツール「ラフールサーベイ」は、1億2000万以上のデータを基に、従来のサーベイでは見えにくかった「なぜエンゲージメントが低いのか?」「高ストレス者のストレス因子は何?」といった低スコアの要因を可視化することができます。メンタル・フィジカルに関するデータはもちろん、eNPSや企業リスクなど組織状態を可視化する上で必要な設問を網羅しています。そのため、今まで気づかなかった組織の強みや、見えていなかった課題も見つかり、「次にやるべき人事施策」を明確にすることができます。
組織改善ツール「ラフールサーベイ」について、詳しくは以下からWebサイトをご覧ください。

6. まとめ
今回はモチベーションを維持する方法や部下のモチベーションを向上させるポイントについて紹介しました。モチベーションの維持や向上は業務効率や労働生産性への向上につながります。さらに社員の主体的な行動を促せると人材育成にも効果が期待でき、組織の活性化を目指すことができます。モチベーションの維持や向上には、社員自身の立場に立った適切なマネジメントやコミュニケーションが不可欠です。
まずは社員が望んでいる働き方や職場環境などのニーズを掴み、効果的な取り組みを行いましょう。