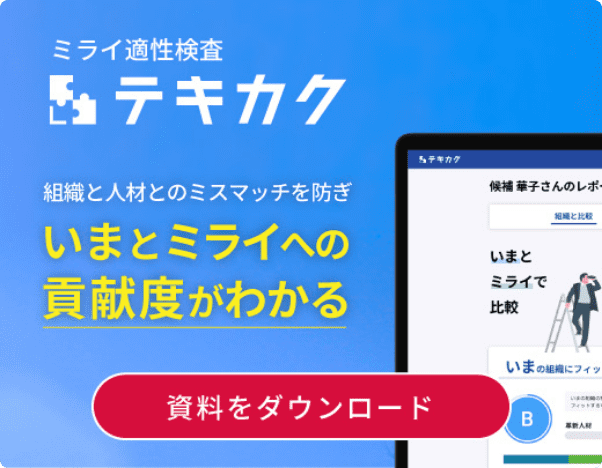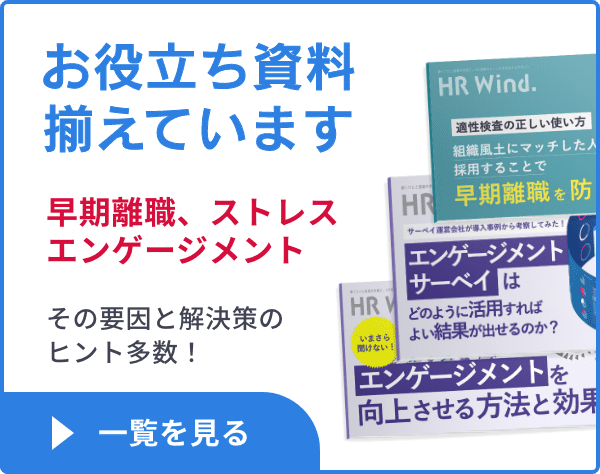新人研修は行っているが、配属後の育成が十分にできていない、せっかく採用した人材が定着せずに離職していくなどの課題を抱いている企業担当者が多く見られます。
近年、入社後3年以内に離職する人々は、全体のおよそ3割にも上ります。また、リモートワークの普及にも伴い、新入社員にとって社内ネットワークを築いたり、スムーズに業務に慣れて能力を発揮したりすることはますます難しくなっています。
そのような中、ビジネスにおいて”オンボーディング”という取り組みが注目されています。ではこのオンボーディングとは、一体どのようなものなのでしょうか。
この記事では、アメリカ発祥のオンボーディングが日本で注目されている背景や、オンボーディングによる離職率の低下、従業員の満足度・組織の生産性の向上などのメリットについて解説します。オンボーディングを実施する際の具体的なポイントを交えながら詳しく紹介するので、自社でオンボーディングを取り入れたいが何から始めればいいか分からない、という方に参考にしていただきたいです。
オンボーディングとは?その目的
元々、オンボーディング(on-boarding)は、「飛行機や船など乗り物に乗っている」という意味の「on-board」を由来とする言葉でした。
一方、そこから派生して生まれたビジネス用語におけるオンボーディングは、新入社員がいち早く組織に順応し、能力を発揮して成果を出せるように上司や人事がサポートする一連の取り組みのことを指します。この取り組みは、新卒入社、中途入社を含む新規採用者全員に向けて行われ、場合によっては社内異動者や出向者も含むことがあります。
オンボーディングによるサポートを行うことで、新入社員だけではなく、組織全体のパフォーマンス向上も見込まれます。
OJTとの違い
オンボーディングと近い意味を持つビジネス用語として、OJTが挙げられます。OJTは、実際の業務を通して新入社員に仕事を教える教育・研修の手法のことを指します。
このOJTに対して、オンボーディングはより広義の意味を指し、新入社員の組織への適応をサポートする取り組みを包括して表す言葉です。これには、交流会や内定者研修、メンター制度など、組織の環境に馴染むためのサポート全てが含まれます。
オンボーディングが注目されるようになった背景
オンボーディングが注目されるようになった大きな要因として、前述したように早期離職率の高さが挙げられます。令和2年度の厚生労働省新規学卒就職者の離職調査によると、大学を卒業して入社した新卒社員の3年以内の離職率は31.2%にも上ります。加えて、中途採用者の3年以内の離職率も30%程度を推移しています。
また、コロナ禍におけるリモートワークの普及も一因となっており、オンライン上で信頼関係を築いたり、業務に関するノウハウを学ぶことが難しくなっています。
これらの要因により高いコストをかけて採用し、教育した人材が短期間で離職してしまうと、企業にとってかなりの痛手となります。
離職の背景には、「入社前と後のギャップ(業務内容、社風、待遇など)」「人間関係になじめなかった」「やりがいを感じられなかった」などの理由があります。いずれも単なる新人研修ではカバーし切れないため、やがて新入社員を組織に定着させるオンボーディングが注目されるようになりました。
オンボーディングを実施するメリット
オンボーディングの実施は、従業員と企業のどちらにもメリットがあります。新入社員が組織に早く馴染めるようになるというメリットに加え、企業にとっては、研修等で教育され、その企業のノウハウを学んだ人物が社内に長く残るというメリットなどが生まれます。また、社内全体において組織の生産性やエンゲージメントの向上などが期待されます。具体的なメリットやその理由は以下の通りです。
離職防止によるコスト削減
オンボーディングには離職を防ぐ効果があります。具体的には、メンター制度や1on1といったオンボーディングを導入することで、新入社員は不安や相談事を気軽に組織へ伝えられるようになります。
また、オンボーディングによって従業員が入社後に感じるギャップを少なくし、モチベーションを得ながら長く働ける仕組みをつくることは、企業にとってもメリットがあります。なぜなら採用活動にはコストがかかり、そのコストはおよそ新入社員1人あたり72.6万円にも上るからです。早期離職を防ぐことで、企業が新たにこの採用活動を行う必要がなくなるため、大幅なコストの削減に繋がります。
組織風土の改善
オンボーディングのプロセスを通して、企業のビジョンや価値観が社内に広く浸透する効果が見込まれます。部署の垣根を越えてオンボーディングを実施することで、人事や教育担当者だけでなく社員全員に新入社員のサポートを行うという意識が備わり、社内のコミュニケーションも促進されるのです。話しやすい風土がつくられることで、新入社員のみならず、教育する側の社員も積極的に自分の意見を発信できるようになります。
また、人事が社内全体にオンボーディングによる様々なプログラムを提供することで、従業員が皆平等な教育と学びの機会を得ることができるようになります。
新入社員の能力がいち早く発揮される

オンボーディングにより入社後スムーズに業務に定着させ、新入社員の成長を後押しすることができます。オンボーディングでは、入社時に新入社員がいち早く組織や業務に馴染めるよう、必要な情報(企業の理念・ミッションから、各部署の役割、各種制度など)を過不足なく提供することが求められます。
配属後のオリエンテーションでは部署の構成・役割・課題など必要な情報を共有しましょう。そして、新入社員が自発的に動き、成果を出せるように会社・部署全体でサポートできるよう仕組み化することが必要です。これにより、新入社員は豊かなサポートを受け、いち早く能力を発揮できるようになり、企業に利益をもたらします。
社員の満足度・エンゲージメントを高める
オンボーディングが仕組み化されることで、新入社員は「入社前の不安が解消された」「自分に期待されている」「周囲のサポートがある」など満足感を感じることができます。また、新入社員だけではなくサポートする側の社員も、オンボーディングを通して業務や環境の見直しをコンスタントに行うことができます。
社員の満足度・エンゲージメントが高まることで、社員の業務に対するモチベーションを維持・向上させることが可能です。オンボーディングの導入は、中長期的にみると会社全体の業績に寄与すると考えられます。
オンボーディングを行うときのポイントと施策/研修例
ここでは、オンボーディングの実施において、人事担当者や新入社員をサポートする社員が留意するべき事柄と、様々な課題を解決するための施策/研修例について解説します。
求める役割や期待値をすり合わせる
新入社員の入社時・配属時に、今後求める役割や期待値を明確に伝えましょう。都度齟齬があれば修正するようにします。なぜなら新入社員の離職に多い理由として、様々な「ギャップ」があるからです。それぞれが持つ認識や考えをすり合わせ、これらのギャップを埋めることで新入社員の離職を防ぐことができます。
転職の理由として挙げられるギャップの例
- 求人内容の待遇・条件と実際とのギャップ
- 想像していた仕事内容とのギャップ
- 求められる能力と実際とのギャップ
社員が期待することと、従業員が認識する内容にギャップが生まれないことが、離職を防ぐ上で非常に重要な要素になります。
施策/研修例
- 経営陣や人事による講習会
- 定期的な面談
- 質問窓口、相談係の設置
- OJT
- 入社前研修
- 内定者インターン
目標を細かく設定する(スモールステップ法)
小さな成功体験を積むことが、新入社員の成長を後押しします。具体的には入社後間もない時期に、3か月〜半年程度で達成できる目標を新入社員とともに立てると良いでしょう。到達するまでに長い期間がかかる目標では成長を実感しづらく、モチベーションを維持することが難しいのです。
達成可能な目標を複数のステップに分けて設定することで、成功体験を得て自己効力感が生まれます。自己効力感が育まれることで生産性が高まります。
施策/研修例
- 個別面談による新入社員の短期的な目標設定
- 目標達成までのサポート
- 成果発表会
学習機会を提供する
研修制度を充実させ、新入社員が研修に積極的に参加するよう促しましょう。その際には、e-learningなども活用すると良いでしょう。
学習機会を提供する際には初期コストはかかりますが、人材への投資は中長期的な視点で見ると利益をもたらします。インプットがなければアウトプットをすることは難しいため、自発的な取り組みを生み出すにも学習機会は必要です。また、学ぶ機会を提供することで、新入社員は「自分に期待されている」と感じ、より満足度やエンゲージメントが高まります。
施策/研修例
- 会社見学
- 社内報等学習資料の提供
- 課題図書やスキルアップ講座の実施
- 企業理念や体制等を学ぶ研修
- 業界知識や技術に関する講義
- 各部署、施設の見学会
- 内定者の交流会
メンター・トレーナーを育成する
オンボーディングのプロセスは、採用時からスタートします。採用から入社までの期間、人事担当者は新入社員とこまめに連絡を取り、信頼関係を築くようにすると良いでしょう。株式会社リクルートキャリアの調査結果(2019年4月)によると、「⼈事によるコミュニケーション」と「⼊社前のオープンで⼗分な情報開⽰」は中途⼊社者のパフォーマンスの発揮に寄与する、と示されています。
採用時に新入社員へメンターを提供し、入社までの期間メールなどで新入社員からの質問に答えたり、相談に乗ったりする制度を持つ企業もあります。これにより、離職の理由に多い「入社前と入社後のギャップ」を埋めることができます。
配属後は先輩社員やOJT担当社員をトレーナーとして割り当て、サポートするようにしましょう。直属の上司以外の「斜めの関係」を築くことで、入社後の人間関係の構築をスムーズにする効果があります。メンター・トレーナーの育成スキルがサポートの質を左右するため、専門機関にスキルアップのためのトレーニングを委託することも有効です。
施策/研修例
- メンター制度
- 1to1
- 先輩社員との懇親会
組織全体で新入社員をサポートする
特定の人事担当者が担う新人研修とは異なり、オンボーディングは組織全体で新入社員をサポートし、育成する仕組みです。リモートワーク中心の企業であっても、オンラインでの交流や相談会を実施したり、メンタルサポートを行うなど、社員一人ひとりがオンボーディングの一翼を担うことができます。
また、社員の顔写真と名前の一致を助け、社内コミュニケーションを円滑にする人事情報システムや、従業員のエンゲージメントの推移を把握するツールもありますので、これらを社内に導入し活用することも非常に効果的です。
施策/研修例
- 全社的な交流会
- ランチ会
- アンケート調査
オンボーディングの導入事例
最後に、オンボーディングを導入した実際の企業例をご紹介します。
LINE株式会社
LINE株式会社は多角的に事業を行っており、加えて年間300人ほど社員が増え続ける状況にありました。そのような中で、中途入社の社員をどのようにしてサポートし、成果を挙げられるようにするかが課題になっていました。
そこで、2017年から「従業員向けパルスサーベイ」と「人間関係の診断サーベイ」を導入し、従業員の変化と課題をいち早く認識できる体制を整えました。
そして、オンボーディングの取り組みとして「LINE CARE」という社内サービスも開始しました。これは、LINEを通じて社員がわからないことをなんでも聞くことができるサービスです。また、「LINE CARE」のサービスカウンターもオフィス内に設置しています。「駆け込み寺」のような存在をつくることで、社員が安心感を持って業務に取り組むことができるような会社づくりを行っています
LAPRAS株式会社
LAPRAS株式会社はフルリモートワーク体制の企業であり、オンライン上でオンボーディングに取り組みました。しかし、その取り組みにはいくつかの失敗があったことに言及しており、その改善点について述べています。
LAPRAS株式会社のオンボーディングは主にZoomのMTG機能を使って行われました。また、1on1やオンライン歓迎会なども行われていましたが、質問がしにくいなど心理的安全性に欠ける点が課題として挙げられていました。
そこで、改善策として挙げられたのが、①雑談による信頼関係の構築、②新入社員と既存社員の認識のずれを埋めることでした。特に②では、メンバー同士で共通認識を醸成するために、議論無しで行う対話型のワークショップであるダイアログという手法が採用されました。
まとめ
オンボーディングは新入社員がいち早く組織に定着し、成果を上げられるよう働きかける一連のプロセスのことでした。これは、特定の人事担当者だけでなく、組織が一丸となって継続的に取り組むアプローチです。
そしてオンボーディングの実施により、離職防止によるコスト削減、組織風土の改善、社員の満足度・エンゲージメント向上などの効果が期待されます。
また、オンボーディングに取り組む際には、新入社員の考えやエンゲージメント、メンタル面を企業がしっかりと把握し、サポートを行うことが重要でした。ここでお勧めしたいのが、ラフールサーベイという組織改善ツールの利用です。ラフールサーベイは個人と組織の抱える課題を可視化し、エンゲージメントを高めることができます。
ラフールサーベイについて詳しくは下記よりご確認いただけます。