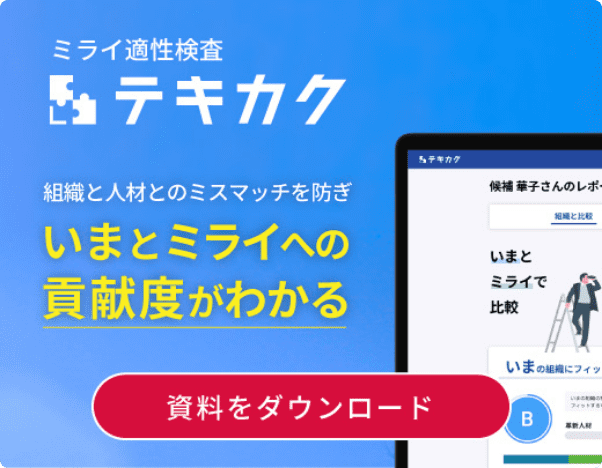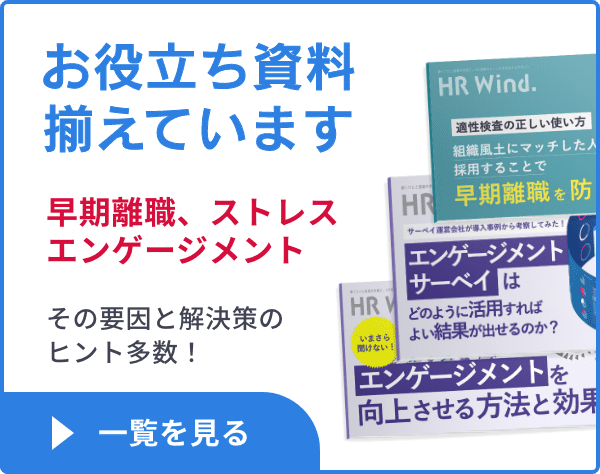「自社の若手育成はうまくいっているんだろうか?」「研修内容を効果的なものにしたい」
マネージャーの方や部下を持つ方であれば、このように若手社員の育成に悩んだ経験は多いかもしれません。時代の流れに伴い若手社員の特徴にも変化が現れている現代では、従来通りの育成では思い通りの成果が得にくいものです。しかし今後会社を背負っていく可能性がある若手社員には、適切な育成を通し飛躍的な成長が求められます。
そこで本記事では、若手育成の課題や方法について、現代に即した内容を解説します。さらに育成におけるポイントについてもまとめているので、マネージャーの方や人材育成に携わる方は、ぜひお役立てください。
若手育成について
若手育成に対し即戦力としての活躍を願い、リーダーやマネージャーの方はさまざまな取り組みをされているでしょう。その一方で、厚生労働省が行った調査では「3年以内に離職する新卒社員の割合は30%」である状況が続いていることが報告されています。そのため、「せっかく育成してもすぐ辞めてしまう」、「研修に何か問題があるんだろうか」などと、思い悩んでいる方も少なくないでしょう。
効果的な若手育成を実現するためには、若手社員が持つ意識を把握し特徴や傾向を捉えた上で内容に取り組むことが重要です。具体的な育成に取り組む前に、まずは若手社員への理解を深めましょう。
【参考】厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」
最近の若手社員の仕事に対する意識
近年の若手社員は、仕事に対するモチベーションが高い傾向があります。
しかしその反面、失敗への恐怖心も大きいことも特徴として挙がっています。
2018年に行われた日本能力協会による「イマドキ若手社員の意識調査2018」では、入社2年目までの社員に対する仕事への意識調査が行われました。
その結果、全体の60.6%が「一時的に業務の負荷や労働時間が増えても(チャレンジングな)仕事に挑戦したい」と回答していることが報告されています。
近年の若者は「ゆとり世代」や「さとり世代」などと呼ばれ、マイペースで無気力なイメージもあるかもしれません。しかし、仕事への挑戦心は多くの若手社員が持っていることが伺えます。
その一方で同調査では、全体の82.9%が「仕事で失敗したくない」という回答もしており、30代後半から50代の世代よりも高い傾向が示されています。
さらに、2018年に行われたアデコ株式会社による「デジタル世代とデジタル世代の部下を持つ管理職の労働や生活に関する調査」では、管理職が感じる若手社員の課題について、調査結果が報告されています。
具体的に課題と思う点としては「打たれ弱さ」が挙げられています。反対に良いと思う点として「デジタルスキルが高い」、「情報収集が速い」といった回答が挙げられました。また同調査で、20代が理想とする上司像として「仕事で困った事について相談に乗ってくれる」の回答がトップに挙がっています。
調査の結果から、近年の若手社員の仕事への意識としては以下の項目が挙げられます。
- 仕事に挑戦していきたい
- 業務での失敗が怖い
- 困った時には相談に乗ってくれる上司がいてほしい
さらに、管理職が感じる若手社員の強みを考慮すると、「デジタル化が進む現代社会において適切なスキルを持ち、迅速な対応ができる」という人物像が伺えます。
最近の新人/若手社員の特徴・傾向
近年の若手社員の特徴や傾向として、「受動的な姿勢」が見受けられます。特に1980年から1995年に生まれた「ミレニアル世代」は、インターネット環境が整った頃に生まれ、さまざまな情報を容易に受け取れる環境で育ってきました。さらに、リーマンショックといった世界的な経済危機に社会人として関わることもなく、何事もほどほどの努力や行動で生きてこられた経験があります。そういった影響もあり、受け身の傾向が見受けられる場合が多くあるのです。
具体的には、以下のような傾向が挙げられます。
- 言われたことはきちんとやり遂げる
- 怒られることや失敗を避ける
- 仕事と家庭どちらもほどほどに取り組む
- 多様な価値観を持っている
これらはあくまでも傾向であり、全ての若手社員が当てはまるわけではありません。しかし、現在の管理職とは全く違う環境で生まれ育った若手社員には、育成を行う立場の人材とは異なる価値観を持っていることは確かです。
若手育成を行う上では、行う側と受ける側で異なる意識や思考を持っていることを改めて理解しておきましょう。
若手育成の課題
近年における若手育成の課題について解説します。改めて育成の目的を振り返った上で、内容を確認していきましょう。
若手育成の目的
そもそも若手育成の目的とは、現場における早期の活躍にあります。育成に何年も時間をかけていては、会社が抱えるコストばかりが大きくなるでしょう。そのため会社にとっては若手社員に対し、なるべく早く現場で成果をあげ利益を生み出す社員になってもらうことが重要です。さらに中長期的に考えると、若手社員が早期の活躍によって着実に成長や経験を積んでいくことにより、10年、20年先の企業の競争力の強化にもつながります。
若手育成の課題
若手社員の課題には、時間や育成スキルの不足、計画性の問題などが挙げられます。2014年に労働政策研究・研修機構によって行われた「人材マネジメントのあり方に関する調査」では、若者層の人材育成の課題として、以下の点が挙げられています。
- 業務が多忙で、育成の時間的余裕がない。
- 上長等の育成能力や指導意識が不足している。
- 人材育成が計画的・体系的に行われていない。
若手育成の目的を達成するには、時間や指導力の確保、育成方法の計画性の高さなどに取り組む必要があるでしょう。
若手育成の方法
若手育成の方法は大きく3つあります。
- 内定者研修・新卒向け研修
- 1on1
- OJT
3つに共通する育成に必要な内容と、それぞれの具体的な方法について紹介します。
若手育成に必要な内容
若手に対するさまざまな育成方法において、共通する指導内容がいくつかあります。
- 社会人としてのビジネスマナー
- 自社のルール
- 会社の経営理念や組織体制への理解
- 業界や部署ごとに必要な知識
- 業務の取り組み方
- 論理的思考力
- 職場でのコミュニケーションの取り方
会社員として社会で活躍する上で必要な内容は、若手育成の機会を通し身につけるよう指導しましょう。
そして具体的な若手育成の機会として、3つの方法を紹介します。
内定者研修・新卒向け研修
入社する前の内定者や、新卒入社の社員を対象とし行われる研修です。対象者となる人材を集合させ、経営方針の共有やビジネスマナーの指導などを行います。会社にとっては、入社前や入社直後にまとめて育成ができるため、あらかじめ若手社員の意識の統一を図ることが可能です。若手社員にとっては仲間となる社員たちと顔を合わせ交流できる機会でもあるため、仲間意識の高まりによってチームで働く意欲が芽生えます。
1on1
上司と部下が1対1で話をする機会を1on1と言います。面談のように堅い雰囲気ではなく、部下が主体となって話をするフランクなミーティングです。上司は部下の話に寄り添い、理解や受け入れる姿勢を示すことによって、部下の主体性や自律性を育てます。部下である若手社員にとって、上司がなんでも話を聞いてくれる機会は、自身の感情や意識、思考の整理を行えます。その結果、挑戦したいと思うことや、仕事へのやりがいを再認識でき、部下のモチベーション維持につながります。
OJT
OJTとは、通常業務を行いながら先輩社員から若手社員に業務の取り組み方を指導する育成方法です。実際の業務を通して行われるため、若手社員にとっては再現性の高い学びが得られます。そのため現場に出た際には即戦力として行動を起こしやすく、経験が少ない若手社員でも活躍に期待できます。OJTの終了後も、慣れない職場の心強い存在として指導者の先輩社員がいるため、悩みや不安を継続的に解消しやすい環境が整います。
管理職向け|若手育成の方法

中長期的に会社の将来を考えると、この先、売上や契約などの成果をあげ、さらなる若手を育て束ねていくのは現在のマネージャーやリーダーではなく「若手社員」です。会社の将来を背負っていく可能性のある若手社員は、適切な育成によって飛躍的な成長が求められます。そして会社の将来に関わる重要な取り組みである若手育成は、管理職による手腕が問われるものです。マネージャーやリーダーが適切な方法を取り入れ成果を発揮するために、管理職に向けた若手育成の方法を4つ紹介します。
コーチング
コーチングとは、個々の強みを引き出し行動力を促進させることで、目標達成を支えるコミュニケーション技能です。社員それぞれが持つ特性や思考を強みとして見いだすため、主体性や自発性を育成できます。そのため、自ら考え行動を起こせる若手の育成に役立てることが可能です。傾聴や効果的な声がけなど、取り入れやすいスキルで行えるため、日常的に育成に励めます。
1on1
1on1は上司と部下による1対1の対話です。部下が主体となり話をすることが特徴です。上司は指示やアドバイスではなく部下の話に寄り添い聞き入れることで、部下は思考の整理ができ自律性を育てられます。面談やミーティングといった形成に囚われず、カジュアルな雰囲気で行うなど、部下が話をしやすい雰囲気を作ることが大切です。
キャリア・コンサルティング
職務選択やスキル向上など、キャリア形成に関する相談を通し成長をサポートする取り組みです。キャリアコンサルティングは資格を有し実施する場合もありますが、上司が部下に対し行う際にも有効です。若手にとっては将来への希望を含めて相談するため、現状で取り組むべき課題を前向きに捉えられます。
サーバント・リーダーシップ
サーバント・リーダーシップとは、上司が部下に奉仕することで部下を導く育成を行う考え方です。一方的な指示や命令ではなく、「部下のために自らが尽力する」ということを意識し若手の自己実現をサポートします。そのため部下には主体的な思考力が身につきやすく、意欲的に課題に取り組むことが可能です。
若手育成をする際のポイント
若手育成には取り組みの際に押さえておきたい4つのポイントがあります。
- 最初が肝心
- 一人ひとりに合った指導方法を考える
- こまめに声を掛ける
- 具体的に指示を出す
1つずつ内容を確認しておきましょう。
最初が肝心
若手には、自身で考え行動できる姿勢を初めから身につけておくことが大切です。一度身についた思考傾向を後から変化させることは困難であるため、初めから育成の必要性や重要性を共有し理解してもらうことで、目指す方向性を統一させましょう。さらに育成の際には単に「教える」のではなく、若手本人による「気づき」を重視します。自身で気づけると、主体性が身につき活発な行動力につながります。
そして、まずは「毎日の業務報告」などの小さな成功体験を積ませていくことや、若手の悩みを共有しやすい環境を整えておくことも重要です。初めのうちから自信を持ちやすい環境を整えておくと、自ら働きかけられる若手育成につながります。
一人ひとりに合った指導方法を考える
若手個々の特性を踏まえた指導法を検討しましょう。若手にとっては自らの特性や強みを引き出してくれる上司は信頼でき、安心して働き続けられます。具体的な方法としては、「自ら問題に気づき対策を考えられる人材」といったように育成によるゴールを設定すると良いでしょう。
ゴールに対して、それぞれに不足している点や強化すべき点を挙げると若手個々の特性を踏まえた育成につながります。また育成担当者には、育成の活動報告を日々共有してもらうよう呼びかけましょう。「職場全体で若手を育てている」という意識をチームに根付かせ幅広い視点で取り組めると、より的確に若手個々に適した育成が可能です。
こまめに声を掛ける
若手は自ら声をあげにくい環境であることを考慮し、こまめな声がけを心がけましょう。「以前教えたからもう大丈夫だろう」といった思い込みはやめ、「以前も取り組んだと思うけどどう?」と若手自身の考えを聞き出すよう意識します。現代の若手社員は育った環境から承認欲求が高い傾向にあり、「認められること」や「求められること」に強い欲求があります。
こまめな声がけは「あなたを気にかけている」という気持ちも伝わるため、継続的な行動を促すためにも意識し取り組みましょう。
具体的に指示を出す
若手に指示を出す際には、具体的な内容で伝えましょう。若手にとって慣れない職場環境では、不明な点があっても「こんなこと聞いたら使えないと思われそう」と萎縮してしまいがちです。そのためまずは具体的な指示を心がけ、報告や提出を受けた際には自身の業務を止めてきちんと向き合い受け入れる姿勢が大切です。そうすることで若手にとっては安心感を抱けて、不明点も自ら伺えるようになります。さらに、ミスや失敗があった場合には責めるようなことはせず、次への対策をともに検討しましょう。
若手育成研修について
若手育成の中でも、研修の実施はメリットの大きい取り組みです。具体的な3つのメリットや、おすすめの取り組み方を紹介します。
研修実施によるメリット
若手向けの研修実施によるメリットは、大きく次の3つがあります。
- 成長実感を得られる
- 帰属意識や会社への愛着心が育つ
- 離職を防ぐ
若手の頃から効果的な育成によって業務での成長実感を得られると、自信や帰属意識の高まりにつながります。「もっと会社のためにも頑張ろう」という意識は、会社での活躍を目指すため離職を防ぐ効果にも期待できるでしょう。
階層別おすすめ研修
若手育成の研修について、1年目から5年目までの階層ごとにおすすめの内容をまとめました。各階層特有の若手社員の悩みに沿って、解決できる方法や研修内容について紹介します。
1年目の社員
1年目では、職場や業務、組織などわからないことが多く不安を抱えている状態です。このような状況が続いてしまうと、自信の喪失にもつながりかねません。そのためまずは、社会人としてのビジネスマナー研修を通し自信を身につけられるよう取り組みます。自らが行うべき言動を明確に把握できると、「なんとかやっていけそうだ」と捉えられ不安の解消につながるでしょう。
2年目の社員
2年目では、与えられる業務に追われ現実と理想のギャップに悩みがちです。そのため「こういう仕事を任されたいのに」、「こんな社会人でいいんだろうか」とネガティブな思考を抱きやすくなります。解決法としては、意欲を上げるために、意欲・モチベーション向上研修や、与えられた業務の目的を理解するための仕事の進め方研修を行うと良いでしょう。業務の全体像を捉え将来への希望を再確認できると、意欲的に業務に取り組めます。
3年目の社員
3年目では、業務への慣れによってモチベーションの低下や将来への不安が見受けられます。そのため、後輩指導研修やキャリアデザイン研修を通し、自らと向き合い仕事に対する価値観を見直すきっかけを与えましょう。後輩への指導を通し自身の成長を実感することや、キャリアデザインの検討で理想像を再確認できます。
4年目の社員
4年目では、経験によって自らの考えで行動できるが故、周囲との対立にも悩む傾向があります。自身の業務だけでなくチームとして働く意識の高まりによって、コミュニケーションに苦戦する場合もあるでしょう。対策としては、レジリエンス研修やコミュニケーション研修を通し、自らの思考力を向上させ適切な協力体制を整えられるスキルの育成を目指します。
5年目の社員
5年目では、チームのリーダーとなる可能性もありマネジメント能力が求められます。しかし初めての立場ともなるため、これまでに経験のない悩みも抱えてしまう時期です。そのため、リーダーシップ研修やマネジメント研修など、立場に合わせたスキルを基礎から学べる研修を実施しましょう。自らに必要な能力を身につけられることで、初めての立場でも自信を持って行動できます。
組織の強みと課題を可視化する 組織改善ツール「ラフールサーベイ」
「あの社員、最近元気がない気がする…」「コミュニケーションをもっと取った方がいいのかな?」とお悩みの管理職や経営者の方も多いのではないでしょうか。
組織改善ツール「ラフールサーベイ」は、1億2000万以上のデータを基に、従来のサーベイでは見えにくかった「なぜエンゲージメントが低いのか?」「高ストレス者のストレス因子は何?」といった低スコアの要因を可視化することができます。メンタル・フィジカルに関するデータはもちろん、eNPSや企業リスクなど組織状態を可視化する上で必要な設問を網羅しています。そのため、今まで気づかなかった組織の強みや、見えていなかった課題も見つかり、「次にやるべき人事施策」を明確にすることができます。
組織改善ツール「ラフールサーベイ」について、詳しくは以下からWebサイトをご覧ください。

まとめ
若手育成は、会社の将来を担う人材への取り組みであり、組織の存続や発展にも影響します。近年では若手社員の意識や傾向にも変化が現れ、従来通りの手法ではなかなか成果が現れない場合もあるでしょう。しかし、若手社員の特徴を踏まえ同じ目線に立つことで、効果的な育成方法を実現できます。
まずは若手社員の意識や傾向を捉え、適切な手法を検討しましょう。