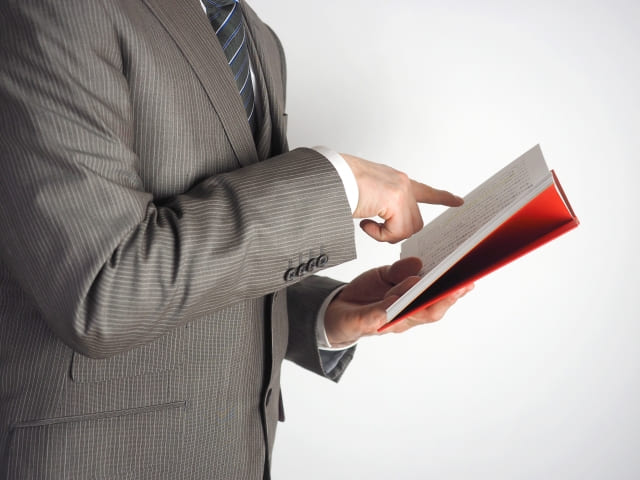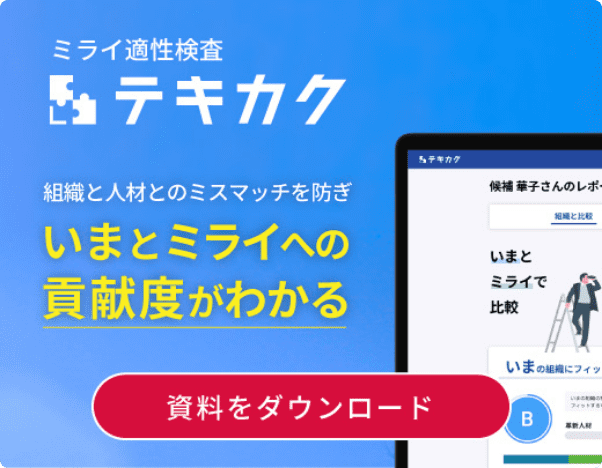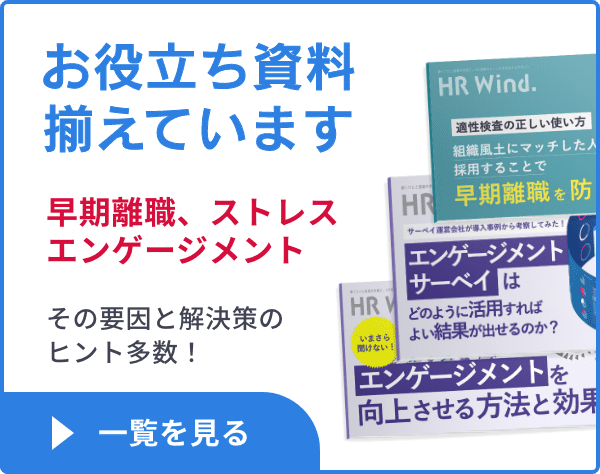自己啓発は、プライベートや仕事で活かせる知識やスキル習得の取り組みを通し、自分自身を高める手法です。取り組みを始める人が増えている一方で、
- 「自己啓発の適切な方法を知りたい」
- 「より効果を高めるポイントを押さえたい」
- 「管理職として仕事で必要な自己啓発ってなんだろう」
このようなことを考えたことはありませんか?
そこで今回は自己啓発の概念やメリット、自己啓発の具体的な方法、自己啓発で向上できる上司のビジネススキルについて紹介します。
さらに既に取り組んでいる方に向けて、自己啓発の効果を高める方法についても解説しました。自己啓発について正しい理解を深めたい方や、具体的な方法について学びたい方はぜひ参考にしてください。
1.まずは自己啓発を正しく理解しよう
自己啓発とは、自分自身の能力を高めることや精神的な向上を目指すことを指します。つまり自らの能力と心の成長を目的とする取り組みです。
自己啓発で得られるメリットは大きく分けて3つあります。
1つ目は「新しい考え方や正しい知識を学べる」ことです。
自己啓発は能力と心の成長のために、新たな価値観を積極的に取り入れます。さらに目指す姿に応じた正しい知識を学ぶ機会も増えるため、これまで以上に視野の広がりが感じられるでしょう。
2つ目は「ビジネススキルの向上」です。
自己啓発で身につける能力には、ビジネスで活用できる能力があります。目指す姿に必要なビジネススキルを学び向上させることで、これまで以上の仕事の成果に期待できるでしょう。
3つ目は「精神的な成長」です。
自分自身の能力の向上により、新たな価値観による視野の広がりや、自分に自信を持てることで精神的な成長ができます。前向きな姿勢が身に付くと、業務の取り組み方や人間関係においてもマイナスな影響が減り安定した気持ちで過ごせることとなるでしょう。
2.自己啓発に役立つ具体的な5つの方法
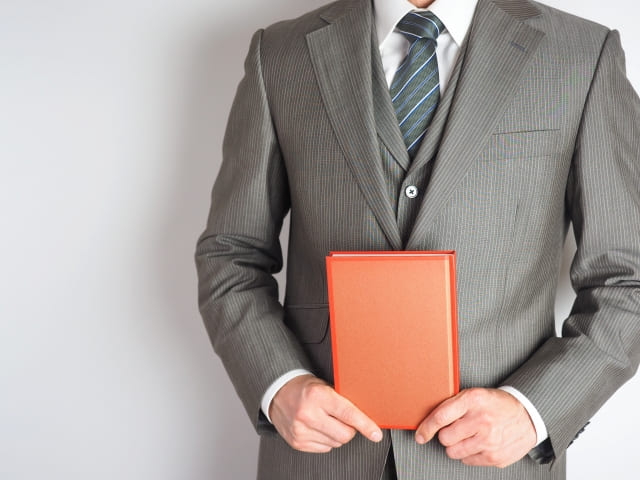
自己啓発に役立つ5つの方法がこちらです。
- 【自己啓発方法①】書籍を読む
- 【自己啓発方法②】講演会やセミナーに参加する
- 【自己啓発方法③】CD・オーディオブックを聞く
- 【自己啓発方法④】eラーニングを活用する
- 【自己啓発方法⑤】ブログを読む
- 【自己啓発方法➅】資格取得をめざす
- 【自己啓発方法⑦】コーチングセッションを受ける
それぞれのメリットやデメリットを解説します。
【自己啓発方法①】書籍を読む
1つ目は書籍を読んで知識やスキルを学ぶ方法です。
手軽で始めやすいというメリットがあり、初めて取り組む場合でも取り入れやすい方法でしょう。
また近年はさまざまな種類の自己啓発本が出版されているため、自分が身につけたい知識やスキルに適切な書籍を選びやすくなっています。
一方でデメリットとして、インプットのみにとどまりやすい点が挙げられます。学んだ内容をアウトプットする機会を積極的に設けるよう心がけるとなおよいでしょう。
【自己啓発方法②】講演会やセミナーに参加する
2つ目は自己啓発に関する講演会やセミナーの場で学ぶ方法です。
講演会やセミナーにおいては専門講師から直接学びを得られるため、より正確な知識やスキルを学べます。また、会場では同じ価値観を持った仲間にも出会えるため、交流を通して情報交換や新たな気づきも得られるでしょう。
デメリットとして出席代のコストが大きくかかる可能性があります。自分が学びたい分野や講演内容を見極めながら、無理のない範囲で参加すると良いでしょう。
【自己啓発方法③】CD・オーディオブックを聞く
3つ目はCDやオーディオブックの視聴で学ぶ方法です。
場所を選ばずに学べるため、通勤途中などの隙間時間を活用し学べるメリットがあります。ただし、書籍で学ぶ方法と同じくインプットにとどまるデメリットも挙げられます。そのため聞きながら内容をノートにまとめる作業や、できる限り日々の生活においてアウトプットできるよう努める必要もあるでしょう。
【自己啓発方法④】eラーニングを活用する
4つ目はeラーニングを活用し学ぶ方法です。eラーニングは導入している会社も多く、比較的取り組みやすいというメリットがあります。自ら申し込み自宅で受講する方法もあるため、学びたい分野を選択し気軽に受講することも可能です。
ただしその場合は受講料がかかるため金銭的負担があります。会社で導入している場合は受講を通し、eラーニングが自分に適しているか見極めると良いでしょう。
【自己啓発方法⑤】ブログを読む
5つ目はブログを読んで学ぶ方法です。
他の方法とは異なるメリットとして、ほとんどの場合お金がかかりません。自分が気になる分野について検索すれば手軽に学べるという点もメリットと捉えられるでしょう。
ただしブログは誰でも発信が可能であるため、記載されている内容が正しい情報かどうか見極める必要があります。執筆している人物の情報や内容の引用元などを確認し、適切な情報であるかどうか注意し学習しましょう。
【自己啓発方法➅】資格取得をめざす
自己啓発に本格的に取り組むと決めたら、資格の取得に励むのも1つの方法です。資格は取得するために必要な知識や技能が明確で、取得した際のメリットも事前に分かります。そのためスケジュールが立てやすいですし、モチベーションもキープしやすいでしょう。
資格を取得すれば知識や技能を学べるだけでなく、キャリアアップにもつながります。履歴書にも書くことができ、自分の成し遂げた成果として、自信を持つことができるでしょう。
【自己啓発方法⑦】コーチングセッションを受ける
コーチングとは目標の達成のために、必要なスキルや理想像などを明確にするためのコミュニケーションのこと。プロのコーチとコミュニケーションを取ることで、自分自身が気づかない内面を知ることができます。新しい視点や考え方にシフトし、習慣を変えることにもつながります。
コーチングは1対1のセッションであるため、テーラーメイドで自分に合った伴走者と一緒に成長できます。
一方、コーチの質や相性に大きく影響を受けるため、必要であれば変更を希望することも大切です。また、コーチングは受講料も高額であるケースが多く、慎重に契約することをおすすめします。本契約の前に体験ができるサービスもあるため、そちらを利用して自分に合うかを判断すると良いでしょう。
3.自己啓発で向上!上司に求められるビジネススキル紹介
部下を持つ上司に求められるスキルはさまざまありますが、中でも自己啓発によって高められるビジネススキル3つを紹介します。
- コーチングスキル
- スケジュール管理スキル
- ファシリテーションスキル
それぞれの内容と効果について確認しましょう。
コーチングスキル
コーチングスキルとは、相手の潜在的な能力を引き出し自主的な行動を促すためにさまざまな手法を用いて指導するスキルです。スキルの種類としては傾聴や質問、承認方法などその場に適したコミュニケーションを図ります。適切なコミュニケーションによって信頼関係が構築され、部下の目標達成に対し効果的なサポートを行えます。
そのためコーチングスキルの向上によって、部下の育成や成長を効率的に進めることが可能です。自主的な行動を促すため、業務に対しても主体的な考えを持って取り組む人材として活躍が期待できるでしょう。
スケジュール管理スキル
スケジュール管理スキルとは、限られた日程や時間の中でタスクや予定を効率よく組み立て実行するスキルです。タスクごとに必要な時間の検討や、緊急や至急の状況にも対応できる高い柔軟性など、スケジュール管理スキルにはさまざまな能力が必要となります。
スケジュール管理スキルの向上は業務効率が改善されるため、残業時間の減少というメリットが得られます。
そのためプライベートの時間をより多く確保することや、新たなスキルを身につける時間にあてられるなど時間を有効活用できるメリットが得られます。
ファシリテーションスキル
ファシリテーションスキルとは、チームとして業務遂行力を高めることを目指し個々のメンバーに対してアプローチを起こすスキルです。ファシリテーションスキルの向上によって、メンバーが互いに気づきや学びを得られるため、チームの力を最大化させることにつながります。
チーム力を最大化させることによってこれまで以上の成果を得られる可能性も高まり、メンバーのモチベーション向上にも期待できるでしょう。
4.実はできていない?効果を高める自己啓発を行う方法
自己啓発の効果を高めるための3つの方法がこちらです。
- 方法1. なりたい自分や人生の目標を書き出して目的を明確にする
- 方法2. 自分にあった自己啓発の方法を選択する
- 方法3. 毎日継続できる時間設定をする
- 方法4. 目標とするロールモデルと話をする
1つずつ具体例を含めて解説します。
方法1. なりたい自分や人生の目標を書き出して目的を明確にする
自己啓発に励む前に、具体的な目的や目標を掲げることによって取り組むべき課題が明確になります。
具体的な目的や目標は紙に書き出すと良いでしょう。可視化することによって、理想と現実のギャップを確認しやすく取り組むべき課題も明確になります。
さらに明確になったさまざまな課題に対して優先順位をつけると、効率良く取り組むことが可能です。課題に対しどんなスキルを身につけるべきか悩んだ場合は、課題の深堀りを行います。具体的には、「なるべく早い退勤を目指すために残業を減らすべきだ」という課題があるとします。
この課題を深掘りすると、残業が減らせていない理由として業務配分が上手くできていない可能性があります。この場合必要なスキルとして考えられる1つとして、スケジュール管理スキルが挙げられるでしょう。
このように、まずは具体的な目的や目標を掲げそのために解決すべき課題を見出すことによって必要なスキルが明確になります。必要なスキルが明確になると取り組む自己啓発にもモチベーションが高まり、より高い効果を期待できるでしょう。
方法2. 自分にあった自己啓発の方法を選択する
さまざまな自己啓発の方法から自分に適した方法を選択できると時間の有効活用が可能です。
多くの人が通常の仕事を行いながら自己啓発に取り組むため、なるべく生活スタイルに適した方法である方が身体的にも負担が少なく継続して取り組めます。
例えば、電車通勤の時間が長い方にとっては書籍やオーディオブックを活用した自己啓発がおすすめです。有限である時間は有効活用できることによって、1日の充実感にもつながるでしょう。自己啓発に取り組む際は自分の生活スタイルを振り返り、取り入れやすい方法を選択してみましょう。
方法3. 毎日継続できる時間設定をする
毎日継続して取り組める時間を検討し設定することで、スキルや知識が着実に自分の能力として身につきます。新しいことを身につけようとする際に最も重要なのは、継続した取り組みです。
短期間で身につけようとしても一度に長時間取り組むことが困難な場合や、表面上のスキルや知識しか身につかない場合もあります。毎日継続して取り組むことによって、学習の積み重ねや課題を乗り越える機会を通し自らの力として身についていくでしょう。そのため、まずは今の自分ができそうなところまでハードルを下げて時間を設定します。
例えば1日10分なら取り組めると考えた場合、その10分間だけ集中して取り組みます。ここで30分や1時間などと、ちょっとでもハードルを上げてしまうと毎日の継続は難しくなっていくため注意しましょう。
毎日無理のない範囲で時間を設定することによって、継続した取り組みを実現でき自己啓発の効果は高まっていきます。
方法4. 目標とするロールモデルと話をする
自分が目標とする人物のことを、ロールモデルと呼びます。ロールモデルとじっくりと話をすることで、目標へ近づくための方法がよりハッキリと見えるでしょう。また目標を達成した人と密接に関わることで、実現の可能性を体感でき、モチベーションも上がります。
5. 自己啓発の注意点
自己啓発をして人間として、そしてビジネスマンとして成長していく際には、以下の3点に注意しなければいけません。
費やす時間や費用をあらかじめ明確にしておく
自己啓発はコーチングや書籍の購入、資格の受験など様々な費用が発生します。また自己啓発をするために必要な時間も、少ないものではありません。まずはどんな目標を達成したいのか、そしてそのためにどれくらいの時間と費用を費やすのか、大まかに目安を作っておきましょう。目安からあまりにも上振れするようであれば、取り組み方に問題がないか、立ち止まって考えることも大切です。
どんな成果があったのか定期的に自己評価する
自己啓発を始めてからどんな成果があったのか、定期的に確認しましょう。スタートの時点で3カ月後、半年後、1年後など目標を設定し、そのタイミングで期待していた成果が得られているかを振り返ります。
目標に到達することができていなければ、課題点をしっかりと分析しましょう。自己啓発を行っているとそれだけで満足してしまいがちですが、ただ行っていれば良いわけではありません。PDCAサイクルをしっかりと回し、改善を繰り返し、成長していくことが大切です。
自己啓発を目的としない
本来の目標や目的を忘れて、自己啓発を行うこと自体が目的化してしまわないように、注意しなければいけません。自己啓発はあくまで目標を達成するための手段の1つであることを、忘れてはいけません。本来の目的や目標を定期的に振り返り、期待した効果が出ていないようであれば、自己啓発のやり方を変えてみることも大切です。例えばコーチを変える、取り組む時間を増やすなど、工夫をしていきましょう。
組織の強みと課題を可視化する 組織改善ツール「ラフールサーベイ」
「あの社員、最近元気がない気がする…」「コミュニケーションをもっと取った方がいいのかな?」とお悩みの管理職や経営者の方も多いのではないでしょうか。
組織改善ツール「ラフールサーベイ」は、1億2000万以上のデータを基に、従来のサーベイでは見えにくかった「なぜエンゲージメントが低いのか?」「高ストレス者のストレス因子は何?」といった低スコアの要因を可視化することができます。メンタル・フィジカルに関するデータはもちろん、eNPSや企業リスクなど組織状態を可視化する上で必要な設問を網羅しています。そのため、今まで気づかなかった組織の強みや、見えていなかった課題も見つかり、「次にやるべき人事施策」を明確にすることができます。
組織改善ツール「ラフールサーベイ」について、詳しくは以下からWebサイトをご覧ください。

6.まとめ
今回は自己啓発について、以下4つの項目に沿って紹介しました。
- 自己啓発の概念やメリット
- 自己啓発を行う具体的な方法
- 自己啓発で向上できるビジネススキル
- 自己啓発の効果を高める方法
自己啓発は新たな視点やスキルを取り入れ自らを成長させられる行為です。
目標を立て学び続けることで、これまで以上に充実した日々を過ごせるでしょう。
その一方で、なかなか時間が取れない場合や、続けられる自信がなく、取り組めない場合もあるかもしれません。しかし自分に合った効果的な方法を見つけられると、少しずつでも自己啓発に努めることが可能です。まずは自分の生活スタイルを思い浮かべながら適切な方法を見つけ、取り組みを始めて見ましょう。