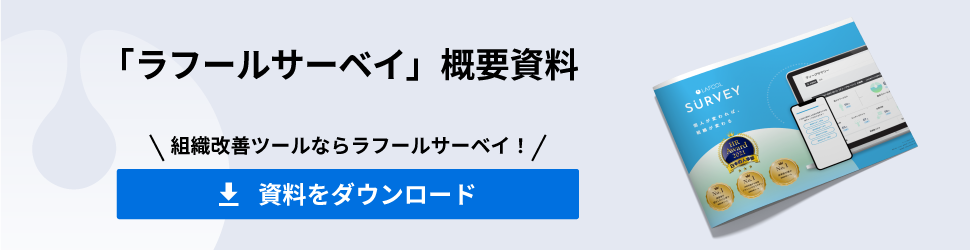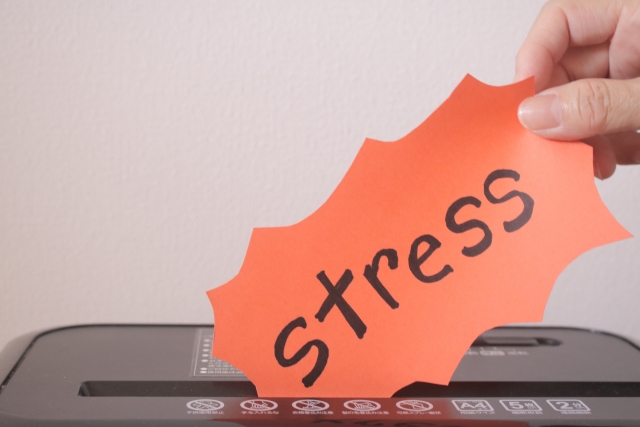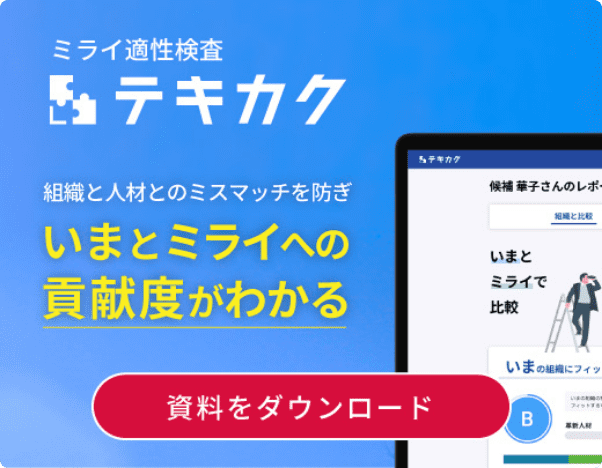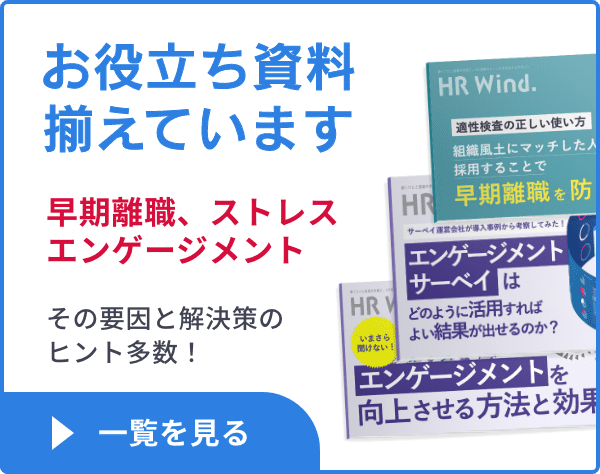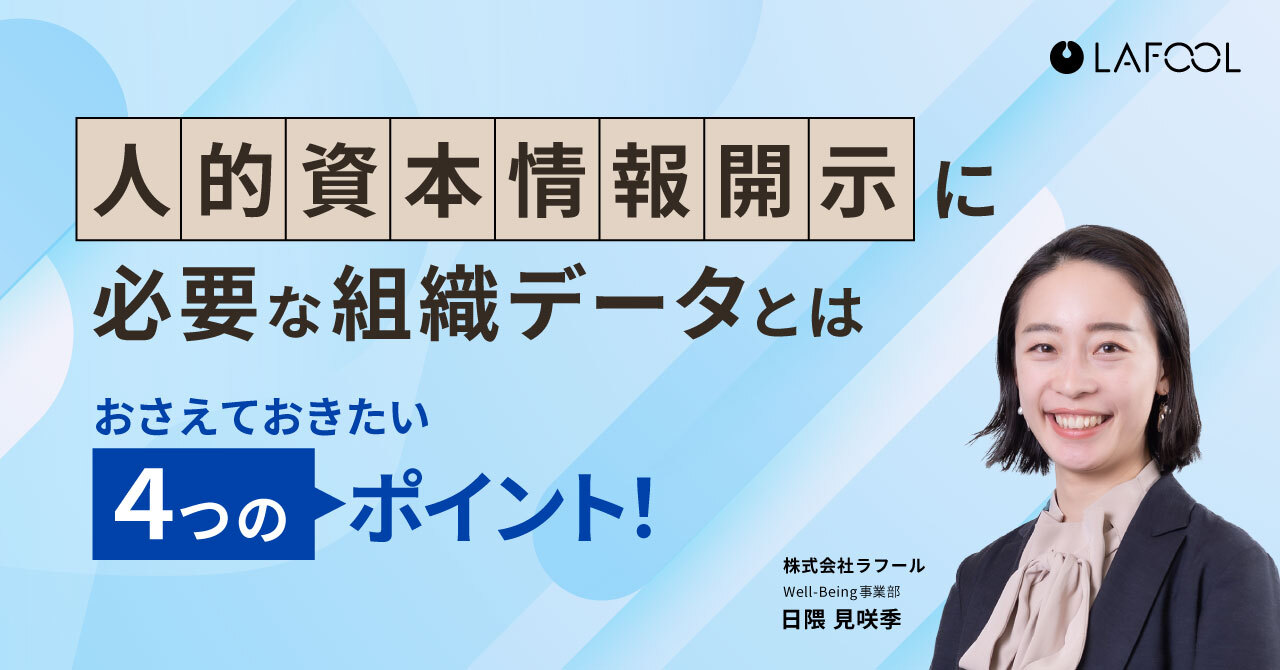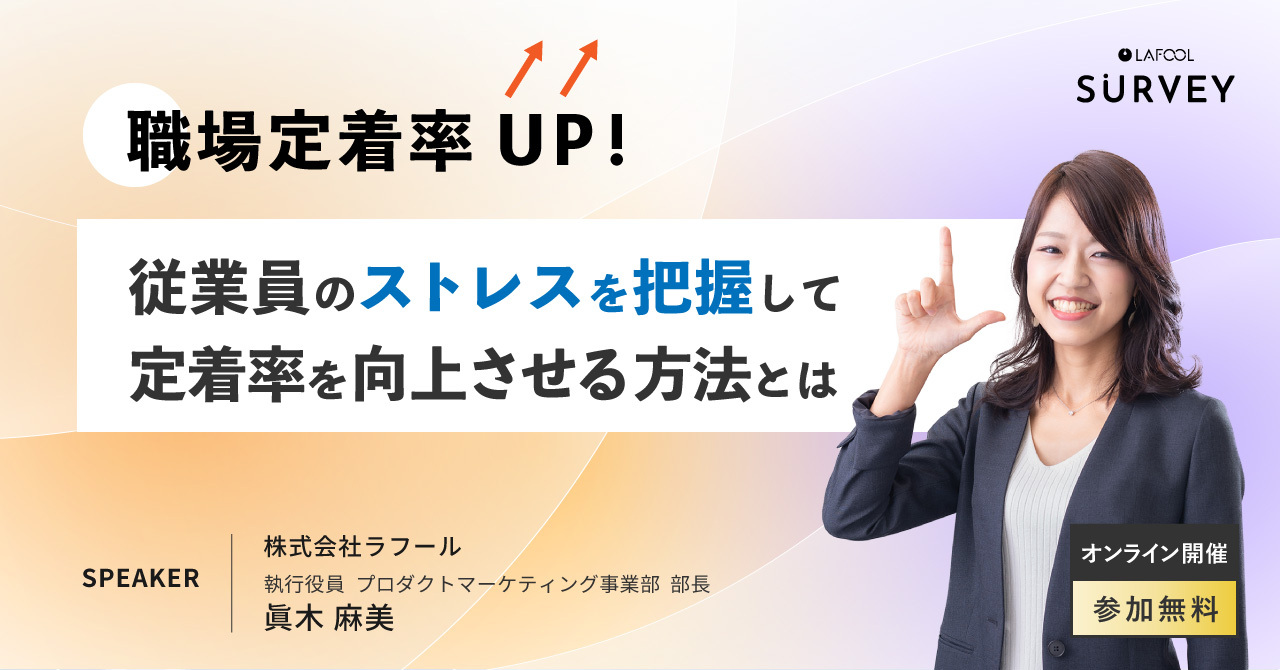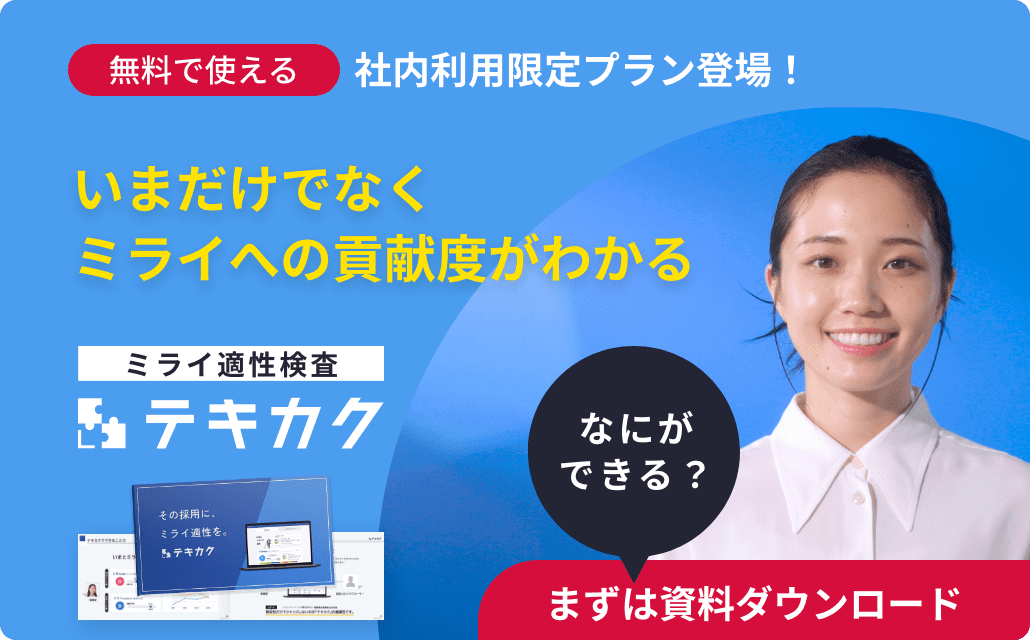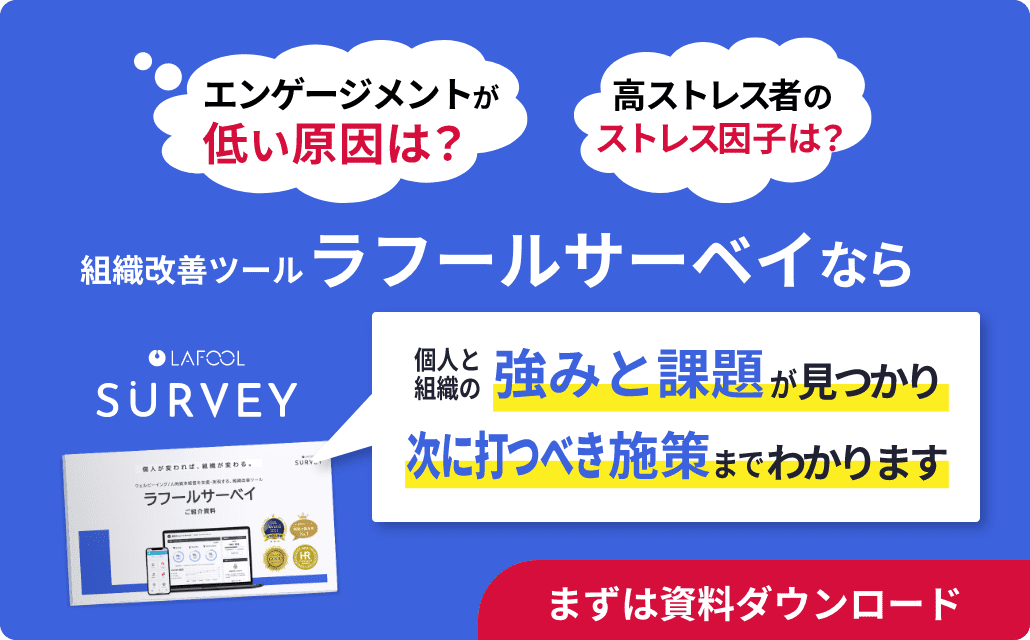仕事では少なからずストレスがあるものです。ストレスは悪いものとされやすいですが、ストレスがなさすぎることも良くないこととされています。
つまり、ストレスはほぼ良くある状態が望ましいので、うまくコントロールする必要があります。
今回は、ストレスをコントロールするときに使える知識「ストレス耐性」についてご紹介します。
ストレス耐性とは

ストレスに耐えられる力のことです。ストレスの原因となることが起きた時、どのように感じて対処するか、どれくらい耐えられるかなどを知る参考になります。
仕事をしていると、忙しい、人間関係に悩んでいるなど、さまざまな原因でストレスを感じます。
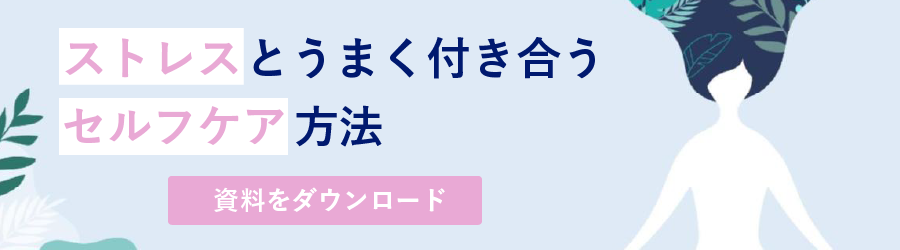
安全衛生法で労働者数50人以上の事業者にはストレスチェックが義務付けられるなど、ストレス耐性は社会でも注目されはじめています。
ストレスチェックは、労働者のストレスの原因を把握し、職場環境の改善につなげるためのものです。
ストレス耐性は6つの構成要素がある
ストレス耐性は、下記6つで決まると言われています。
- 容量
- 処理
- 感知
- 経験
- 回避
- 転換
それぞれ、ストレスの感じ方や対処方法に影響します。
容量
ストレスを溜められる程度を表します。大きさによってストレス反応、ストレスが原因で引き起こされる心身への影響の出やすさが変わります。
容量が大きいと、ストレスを感じてもすぐには不調になるとは限りません。小さいと、ネガティブな感情や持病によらない身体の不調などが起きやすくなります。
処理
ストレスの原因となる出来事に対処する能力です。力は、ストレスを感じにくくするための対応ができるか、原因をなくせるかなどで変わります。
たとえば、残業の多さがストレスの場合。残業時間を短くしたり残業したりしなくても成果を出し続けるために、業務の進め方や時間配分を見直せるなどは、処理能力があると言えます。
感知
ストレスになり得ることに気付くことです。たとえば、「今度から〇〇のように進めてください」と直接言うのではなく、「普通〇〇ってやるよね」と他の人に話しながら聞こえるように言うなど、嫌味っぽい言い方で上司から注意を受けた時。
上司が悪意を持っていると感じれば、ストレスになります。一方、相手の伝え方が気にならないなら、ストレスにはなりにくいです。
感知する力が高い、つまり、相手の態度や環境の変化などを感じ取りやすい人ほどストレス耐性は弱く、感じ取りにくい、良い意味で周囲に無関心な人ほどストレスには強いと言えます。
経験
これまでどのようなストレスをどれくらい受けてきたか、ストレスを感じた時どのように対処したかなどを指します。似た体験をするほど、ストレスに強くなるのが一般的です。
たとえば、就職・転職活動中の面接。最初はうまく行かず「どうしてスムーズに話せないのか」「どこも決まらないかも」と不安でも、回数を重ねると慣れてきて、次の面接に向けて対策をとれるようになった方は多いのではないでしょうか。
ただし、考え方のクセによっては、同じような経験を繰り返して耐性が低くなることもあります。
先の面接で例えると、うまくできなかった原因を分析し、次に活かそうと考えられる人は、ストレスに強くなる経験を積める人です。「何回やっても上達しないから成功するはずがない」と考えてしまう人は、経験で耐性が弱くなるタイプです。
回避
ストレスになり得ることを深刻にとらえず、流せることです。物事の割り切りが得意な人は回避能力が高く、完璧主義や几帳面過ぎる人は低い傾向にあります。
心身が健康だと、能力が高いとも言われています。自律神経系、内分泌系などと回避能力は関連があると考えられているためです。
たとえば、苦手な人とチームを組むことになった時。回避能力の高い人は、「苦手な人がいない人なんてあり得ない」と考え、業務に支障のない最低限の接し方ができるでしょう。一方、回避能力の低い人は、何とか仲良くなろうと頑張り過ぎて、ストレスが蓄積されるかもしれません。
転換
ストレスにつながる出来事をポジティブに捉えられることです。
転換が上手だと、仕事量が多いと感じた時、「残業しないと終わらなそうで嫌」「疲れた」と感じる前に、「仕事の進め方や時間の使い方を見直すきっかけになった」「この仕事をこなせたら、難しいことも乗り越える力がつくだろう」などと考えることができます。
ストレス耐性が高い人と低い人
性格は、ストレス耐性を予測する参考になります。
ストレス耐性が高い人の特徴
ストレスに強い傾向のある人の特徴は、ポジティブなことです。性格ごとに理由をご説明します。
前向きに捉えられる人
困難なことも難しく考え過ぎず、今後に活かせるチャンスと考えられる人です。仕事は順調なことばかりではありません。うまく行かない時、悩んだり躊躇したりするだけでは状況を変えられず、自分が何もできないと感じてストレスになることが懸念されます。
一方、「今度は違うやり方を試してみよう」「新しいことに挑戦できて良かった」と考えられると、うまくできなかったことを成長のきっかけと見なすので、ストレスを感じにくいです。
楽観的な人
考えているだけではなく、切り替えの大切さも分かっている人です。ネガティブに考え過ぎると、何もできないばかりか、状況が悪化することもあります。
たとえば、進捗報告をして大がかりな修正を依頼された時。「締切に間に合わないだろう、どうしよう」と悩むだけで着手しないと、終わるものも終わりません。
「納品前に間違いに気付けて良かった」「良いものを提出できそう」と思えれば、締切に間に合わない不安は抱いていません。結果、ストレスになりにくいです。
集中力がある人
今すべきことに無我夢中で取り組める人です。たとえば、予定外の緊急の仕事を頼まれても、慌てず片付けられるような人です。
目の前のことに集中していたら、余計な心配をしなくて済みます。
仕事でもプライベートでも、想定外のことは起こり得ます。予想外のこともうまく対処できれば、忙しいことが気になったり、仕事が終わらないかもと不安になったりする時間は生まれないでしょう。
ストレス耐性が低い人の特徴
ネガティブな人は、ストレスに弱い傾向があります。
几帳面な人
まじめで、何事も完璧にしないと気が済まない人です。たとえば、仕事の進捗を報告する際、完成形でないと報告しにくいような人です。
どのようなことにも手を抜かないで取り組めるのは素晴らしいです。しかし、全てに高い質を求めることは、自分を苦しめることになります。少しでもうまく行かないことがあると自信を失い、追い詰められてしまうかもしれないためです。
責任感が強い人
他のメンバーのことを考えられる、自分の仕事を最後までやり遂げられる、といった人です。
メンバーシップを持っている、安心して仕事を任せられるなどは、社会からの評価は高いです。しかし、目標ややり方を変えるといった柔軟な対応が苦手と見られることもあります。
大きな目標達成がすぐには難しくても、小さな目標を立ててクリアしていけば、達成感は得られます。慣れたやり方よりも新しい方法の方が、効率的なこともあります。
責任感が強いと、「自分で設定した目標ややり方でなければならない」と固執してしまう人もいます。思い込みから、自分が追い詰められてしまいます。
神経症的傾向が強い人
何事も深刻に捉えてしまう人です。たとえば、お客様からクレームを言われたなどを、プライベートの時間でも悩み続けるような人です。
悩んでばかりだと、目の前の仕事が手につきません。「うまく行かない」「終わらない」など、さらなる悩みが生じます。
気持ちの切り替えが苦手なことも、ストレス耐性が弱い原因です。プライベートでも仕事の悩みの種について考えてしまい、ストレス解消の機会が失われます。結果、ストレスが溜まり、ストレスが原因の不調が引き起こされる可能性が高まります。
ストレス耐性を鍛える方法
ストレス耐性は高めることができます。3つの方法を具体例と併せて紹介します。
ストレッサーを確認する
ストレッサーとは、ストレスの原因のこと。何がストレッサーになりやすいか、要するに、どのようなことにストレスを感じやすいか知ることが大切です。
ストレスになりやすいことを知り、ストレスを感じるとどのような反応をする傾向があるか分かると、物事の見方を変えてストレスを抱える前に流せるようになるでしょう。たとえば、難しい仕事を頼まれたら「成長のチャンスをもらえた」など。
ストレッサーを完全になくすことはできません。しかし、なくせそうなものなら、ストレッサーを防いでストレスを感じないようにするための対策をとれます。たとえば、職場が適温でなくて集中できないことがストレスなら、エアコンの温度を調整してもらう、体温を調整しやすい服装にするなどで対処できます。
コントロールできるものとできないものを整理する
ストレスの原因は、自分で対処できるものとできないものがあります。自分の思考のクセなどが原因なら、見方を変えるなどでストレスが和らぐかもしれません。
一方、他者や環境が原因だと、簡単には変えられません。たとえば、苦手な上司がいるとします。相手の性格や態度は、自分では変えられません。上司と距離をとりたいと思っても、部署異動はすぐには難しいもの。
しかし、「合わない人がいるのは普通のこと」と思えれば、人間関係の悩みを減らせそうです。
コントロールできないものに悩んでも仕方ないと思えるだけでも、ストレスは感じにくくなるでしょう。
リフレッシュする方法をストックする
ストレスが蓄積されないよう、ストレスを感じたら解消することも大切です。
ストレッサーの捉え方を変えるなどが必ずしも効くとは限りません。ストレス耐性が強い人でも、蓄積され続けると心身に不調をきたす恐れがあります。
ストレスを溜め込まないためには、リフレッシュ方法を持つこともポイントです。たとえば、栄養バランスの良い食事、十分な睡眠、深呼吸、軽い運動やストレッチ、趣味に打ち込むための時間などです。
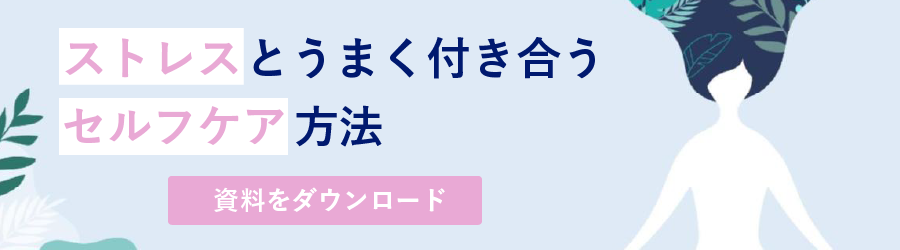
ストレス耐性の調査方法なら「ラフールサーベイ」
「ラフールサーベイ」は、従業員の状態の可視化に役立つツールです。従来の社内アンケートなどでは見えにくいメンタル・フィジカル・エンゲージメントなどを可視化することで、社員が安心して働ける環境づくりのお手伝いをします。
ラフールネス指数による可視化
「ラフールサーベイ」では、組織と個人の”健康度合い”から算出した独自のラフールネス指数を用いて、これまで数値として表せなかった企業の”健康度合い”を可視化できます。また、他社比較や時系列比較が可能であるため、全体における企業の位置や変化を把握することも可能です。独自の指数によって”健康度合い”を見える化して、効率良く目指すべき姿を捉えられます。
直感的に課題がわかる分析結果
「ラフールサーベイ」の分析結果は、グラフや数値で確認できます。データは部署や男女別に表示できるため、細分化された項目とのクロス分析も可能です。一目でリスクを把握できることから、課題を特定する手間も省けるでしょう。
課題解決の一助となる自動対策リコメンド
「ラフールサーベイ」の分析結果には、対策案としてフィードバックコメントが表示されます。良い点や悪い点を抽出した対策コメントは、見えてきた課題を特定する手助けになるでしょう。
144項目の質問項目で多角的に調査
「ラフールサーベイ」で従業員が答える質問項目は全部で144項目。厚生労働省が推奨する57項目に加え、独自に約87項目のアンケートを盛り込んでいます。独自の項目は18万人以上のメンタルヘルスデータをベースに専門家の知見を取り入れているため、多角的な調査結果を生み出します。従来のストレスチェックでは見つけられなかったリスクや課題の抽出に寄与します。
ヴィス社と提携しメンタル・エンゲージメントサーベイツール「ココエル」を提供開始
ダウンロード資料のお知らせ
ラフールサーベイの機能や特徴を3分間でお読みいただける資料にまとめました。資料は以下からダウンロードしていただけます。
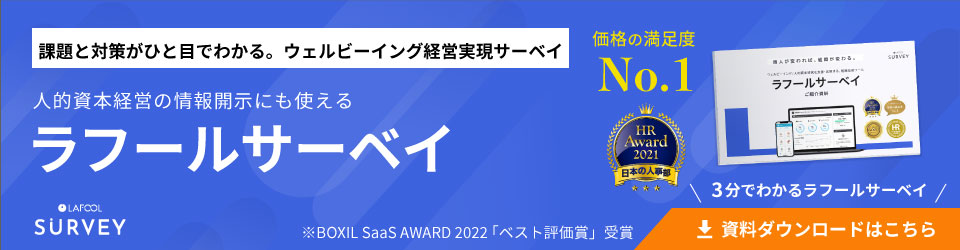
社員が安心して働ける環境づくりは、企業の成長・拡大のための土台となります。まずは、社員一人一人にとって居心地の良い職場を整え、人材の定着と組織改善につなげましょう。
まとめ
仕事をしていれば、ストレスを全く感じないのは難しいでしょう。しかし、ストレッサーと言える出来事があった時、捉え方を変える、まずはできそうなことに取り組んでみるなどで、心身に不調が起きるほどのストレスは避けられそうです。
ストレスを感じやすいことを把握する、ストレス解消法をストックするなどで、ストレス耐性は高められます。ストレスと上手に付き合い、心身の健康を維持しながら働けるようにしましょう。